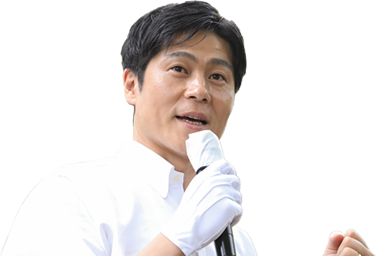下請法(下請代金支払遅延等防止法)改正案について、理事にご配慮をいただき、経済産業委員会で質問をさせていただきました。
冒頭、トランプ関税が価格転嫁や賃上げに与える影響について質問し、中小企業やその従業員の方の安心となるようなメッセージと具体策を打ち出すよう求めました。
下請けに関しては、建設業が下請法の適用から除外されている点や公共事業等の入札における適切な価格転嫁への配慮、価格転嫁の話し合いにおける親事業者の責任などについて議論しました。
また関連して、除雪の人手不足を踏まえて、下請けを含む除雪事業者を、雪の多寡にかかわらず支える仕組みの必要性を訴えさせていただきました。
地方では元請けも下請けも中小であり、不可欠の存在です。地元では両者の関係は良好とも聞きますが、元受け下請け関係なく適切な収益が得られるよう、ひきつづき注視して参りたいと思います。
4月16日経済産業委員会(下請法)質問案
1.トランプ関税の影響と中小企業支援の必要性について(経産)
〇まず冒頭、第2次トランプ政権の関税政策によるわが国への影響について伺います。
石破総理は一昨日、連合芳野会長との政労会見において、「賃上げこそが成長戦略の要との認識を持ち、物価上昇に負けない賃上げを早急に実現、定着させていきたい」と発言されています。
しかし、その要となるべき賃上げについて、トランプ関税の影響が懸念されます。この点芳野会長は、会合後に、「中小の賃上げの環境整備について政府から協力が得られた」と述べておられますが、この「協力」とは具体的にどのようなことか、まずお伺いします。
〇今年の春闘では昨年からの賃上げの流れが継続しているとされますが、実際には1/3の労働組合でまだ春闘が終わっておらず、その多くが中小企業です。私の地元新潟でも、連合傘下の組合のうち約八十がこれからとなっています。
本法案は賃上げのため適切な価格転嫁の定着を目指すものですが、総理が「成長戦略の要」と述べた賃上げの実現に向けて、価格転嫁をどのように位置づけているか、価格転嫁こそが成長戦略の要という認識でいいのか、政府の認識をお伺いします。
また総理は、「あらゆる政策を総動員する」「中小企業に関税問題のしわ寄せがいくことがないように(したい)」と発言されています。この「政策の総動員」の中身についても具体的にお答え願います。
不安を抱えて状況を注視している中小企業とそこで働く方々に届くように、総理のご発言をもう少し具体的なメッセージとしてご説明をいただくとともに、併せて、適切な支援を早急に講じる決意を伺いたい。
〇私の地元の新潟県のような豪雪地帯では、冬はずっと除雪をしなければなりません。この除雪を担っている除雪事業者は何者かというと、一般には地域の土木・建設業者です。重機の扱いなどに慣れているというのもありますし、雪に閉ざされる冬には工事ができませんので、建設工事の仕事がないということもあります。
ところで下請法(下請代金支払遅延等防止法)、改正前なのでそのまま呼ばせていただきますが、「建設業者が業として請け負う建設工事」は本法の適用を除外されています(第2条第4項)。まず、なぜ建設工事が除外されているのかうかがいます。また、建設業者が行う除雪は下請法の適用対象なのか、対象外なのか併せてお伺いします。
〇建設工事は、建設業法で類似の規制があるとして、平成15年改正で除外されたものです。
しかし近年、下請法違反行為に対する公正取引委員会による勧告、指導などの件数は増加傾向です。原状回復していただく金額も増加しています。建設業法でも、下請法違反に相当する行為があった場合は、国交大臣が公正取引委員会に措置要求をすることになっています。では、この措置要求が行われた件数、公正取引委員会の措置につながった件数はどれだけありますか。お答えください。(公取委員長)
→件数ゼロ
(指摘)建設業法の観点から必要な指導等はしているとのことですが、全くないというのはどうなのでしょうか。そもそも、中立な立場の公正取引委員会による指導・勧告と、業界を所管する省庁による指導・監督は意味合いも異なるのではないかとは指摘しておきたいと思います。
〇私の地元は地方ですので、下請けというと、まず土木建設業が挙がるわけです。今回の質問にあたって、地元で様々な事業者の方のお声をうかがいましたが、多くが建設業者の方でした。今回の下請法改正の大きな背景は価格転嫁ですが、建設業の価格転嫁率も50%前後、業種別で12位と、特に価格転嫁が進んでいるという訳でもありません。
先ほど確認したように、工事に必要な資材作成の発注、除雪など、建設業でも取引の種類によっては下請法の適用を受けるわけです。下請法の適用の有無が、現場でも本当にきちんと理解できているでしょうか。
建設業法によって、建設業界に即した規制や指導を行う必要性は否定しません。しかし建設業もそれ以外の業種も、広い意味で独禁法の「優越的地位の濫用」の禁止の規制が及ぶわけです。優越的地位の濫用を防止する観点に特化し、様々な業種を包括的に規制する下請法の規制を建設業に及ぼしてもよいのではないか、わざわざ建設業だけ適用を除外する必要はないのではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。
→国交省が業界に即した規制をしている、という類の答弁かと思われる。
(更問)例えば食品表示には、食品表示法・JAS法・景品表示法など異なる法律が重複して規制がかけられています。また昨年のトラック運送の法改正では、書面提出義務について下請法と重複するところ、下請法の書類提出をもって業法の提出義務を満たすという整理も行われています。
類似と言っても、下請法と建設業法の規制は同じではなく、建設業法とは観点が違うところも多いはずです。建設業にも下請法の規制を及ぼし、それぞれの観点から別々に規制をかけても問題ないのではないでしょうか。類似の規制がある建設業法とそのまま重ねて適用することに課題があるなら類似規制は整理すればよいと考えますが、重ねて見解を伺います。(大臣)
(指摘)
建設業では下請取引が一般的で、下請けと言えば、やはり建設業を思い浮かべます。下請け一般を規制する法律から、建設業だけ除外されているというのは、大半の国民にも理解しにくいことですし、また業界を所管する省庁と、行政委員会として独立性を持ち、競争の番人などと言われる公正取引員会では立場も違います。国土交通省も適正な指導監督に努められているとは思いますが、下請けにとっても、公取が中立の立場から見てくれている方がより安心につながるのではないかと、指摘はしておきたいと思います。
〇話を戻し、除雪について伺います。先ほど申し上げたように、豪雪地帯では、地域の建設業者の方が冬場に「除雪」を担い、いわば地域の暮らしと経済を支えるインフラを担っていただいているわけです。
ただ除雪という仕事は特殊でして、まず「いつ仕事が発生するか」は天候次第です。命に直結する仕事ですので、「降ったら即座に動く」ことが求められますが、雪が降っていないときも事業者の社員には生活があり、給料を支払わないといけない。今年は雪が少なかったから無給、という訳にはいかないのです。
雪国では冬に工事ができません。除雪の仕事もあるかないかとなると、従業員を養っていけないため、建設業者は生活のため出稼ぎなどで地元から出ていくことを考えざるを得ません。このため、私の地元では近年、除雪の人手の確保のため事業者の方に「待機料」という制度を設け、雪が少ない場合でも一定の補てんをしています。これは、雪が少なくても最低限これだけは払いますという、最低保障のようなものです。
例えば新潟県は、11月15日から3月まで、県道の除雪に備えてワンシーズン機材と人を拘束する代わり、一時間あたり8千円を、山間部なら246時間分、平地なら123時間分、海岸部なら82時間分を、人件費分の待機料として支払います、という制度にしています。除雪機械を出してもらう場合は、別途機材の管理料も負担します。また市にも市道などの除雪のため、待機料を支払う制度があります。私の地元の市の一つでは、最大で180時間分です。
ただこれでも、4か月で数十万円~百数十万程度ですので、一人分の人件費としてもギリギリです。実際には、新潟では、除雪車を安全のため2人体制で動かします。人手不足の中、他県ではワンオペをする自治体もあるようですが、除雪機というのはむき出しでブレードが回る大型機械が、見通しのきかない中で生活空間を動く危険なもので、実際、除雪機による事故の死者が毎年絶えません。しかし、安全のために必要な2人目を待機させておくお金が出ない、これが現実です。事業者からは、「何もなかった時よりはましだが、厳しい状況に変わりはない」「下請けにも備えていただくお金を出したいが、今の待機料では難しい」という声が上がっています。
これは下請法から少し外れますが、国交省に伺います。私は、除雪の体制を維持するため、その年の雪が多い少ないにかかわらず従業員の収入を確保し、事業者を支える施策が雪国では必要だと考えます。また、申し上げたように除雪は2人体制で動かすのが現実ですが、今申し上げた地元の仕組みでも、この実態を前提として支える制度には届いていない。自治体が設けている制度、自治体によって違うのかもしれませんが、このことをどう思われますか。
〇国としては、除雪の経費としての自治体からの申告に基づき、一括してお金を出しているだけかもしれません。であれば、安全を考え二人体制で回す現実を踏まえ、そういう体制を前提に請求していいと、自治体が財源を心配しないでいいとして頂きたいと考えます。実際、高速道路の除雪では、待機期間も含め2人とも報酬が支払われているとも聞きます。ぜひ、現実に即した支援をお願いしたい。
また、もしこういう「待機料」という仕組みが一般的でないのなら、豪雪地帯の除雪体制、生活を守るために、ぜひ全国の豪雪地帯で導入が進むようにしていただきたいと考えますが、ご見解を伺います。(国交)
〇ただでさえ地方では建設業者の経営は思わしくありません。都市部で建設需要がひっ迫している中で、このままでは、中小の事業者はどんどん都市部へ出稼ぎに出ざるを得ません。除雪の体制が維持できなくなりかねなませんし、また中小事業者の、地方・雪国からの流出は、一極集中の是正を目指す政府の方針にも逆行すると考えます。
雪国の除雪体制を守り、中小事業者の流出を防ぐことは、単に一地方の問題ではなく、日本の半分に及ぶ豪雪地帯とそこに住む1900万人の切実な問題であり、日本全体の課題だと考えます。大臣の見解を伺います。(経産大臣)
4.「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置」について(経産、国交、財務)
〇次に、公共の入札における賃上げへの配慮について伺います。
令和3年の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を受けて、「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置」という制度が運用されています。これは簡単に言えば、賃上げを促すため賃上げを実施した企業を公共事業等の入札で加点し優遇する仕組みです。これは国土交通省だけでなく経産省ほか各省庁で実施されています。
ただこの仕組みは、国や自治体から直接受注する事業者が対象であり、当該事業者の中で、大企業なら3%、中小企業なら1.5%の賃上げが行われていることを求めるもので、下請けの賃上げは関知していません。そこで伺いますが、下請けにおける賃上げ、ないし下請けへの価格転嫁を適切に行っている企業を優遇する仕組みはありますか。制度を所管する財務省に伺います。
〇この制度の元となった社会全体で賃上げを実現するという政府方針、今回の法案のめざす価格転嫁の実現を踏まえれば、単に入札企業の賃上げだけでなく、価格転嫁を適切に行っている親事業者を優遇する制度を設けるべきではないでしょうか。
この加点措置の制度内に組み込む必要はありませんし、価格転嫁をどのように評価するかの制度設計も考えなければなりませんが、そうした取り組みをする必要性について、ご見解を伺います。(財務省)
(社長からの相談事項)
〇ところでこの加点措置は、落札者である事業者の会社内全体で賃上げを行うことを要求しています。しかし公共事業が減る中で、とくに私の地元のような地方では、中小・中堅の事業者でも建設業のほかに様々な事業を展開し、多角化を図ってきています。
しかしたとえば建設工事の入札でこの加点措置を受けた場合、建設部門だけでなく、他の部門でも同様に賃上げをすることが求められるのです。社会全体で賃上げを促すことは非常に重要なことと私も思いますが、受注と関係のない部門、実際に入札によって売り上げを得るわけでもない部門の賃上げも条件とすることは適切なのでしょうか。
単年度1.5%ならまだしもですが、継続して毎年公共事業を受注する企業では、継続して賃上げを続けなければならず、もし賃上げができないと重いペナルティが課されます。地元では中堅を中心に、公共事業から手を引かなければならないかもしれないという声も聞いています。
他部門を分社化しグループ会社にすれば、賃上げの義務を逃れられるとも聞きます。であればそもそも、公共調達を受注した当該部門だけに賃上げを求めればよいのではないですか。(財務)
(人事異動で義務を免れうるという指摘に対して)
一部の不心得者への対応のために、すべての企業に負荷をかけるのは違うのではないでしょうか。構成員に多少異動があるのは部署単位であろうと会社単位であろうと同じだと考えますし、また現行の仕組みでも、グループ内の人事異動で義務を免れうることを考えれば、理由として不十分と考えますがどうでしょうか。
〇経産大臣、いかがでしょうか。今申し上げたように、制度のあり方は考えなければなりませんが、受注企業だけでなく、下請けへの価格転嫁をきちんとしている事業者を優遇するしくみをご検討いただけないでしょうか。例えば、建設なら基準労務単価をきちんと守って下請けに発注しているとか、基準も何か考えられるのではないかと思います。
私の地元では、どこも人手不足で下請けを大事にしないと受けてもらえず仕事が回らない、下請けを大事にしないところは淘汰されるという話も聞きます。しかしそうでないところもあるからこそ下請けの問題は尽きないのだと思います。
二つ目の当該部門だけか会社全体かという点についても、継続的な受注が難しくなるという現場の声を、どうか真剣に受け止めていただきたい。もし声が届いていないなら聞いていただきたいと思います。
ご答弁を願います。
5.「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」にかかる親事業者の責務について(公取)
〇次に、本改正の重要なポイントである「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」、価格転嫁のための親事業者と下請事業者との話し合いについてお伺いします。
地元を回っていますと、「親事業者と交渉できているか」という点は、現場の声が本当に二極化していると感じます。最近は、「親事業者ときちんと協議できています」という声は確かに増えています。制度が変わって、少しずつ対話の機運が出てきたという評価もある。しかし一方で、「うちは一度も協議を持ちかけられたことがない」「そんな雰囲気すらない」「持ちかけたら仕事がなくなるんじゃないかと不安だ」という声も、同じくらい聞きます。
重要なのは、「跳ね返された」というよりも、そもそも「話し合いすらしていない」という声が多いという点です。今回の改正で、「協議に応じる義務」が設けられますが、親事業者が「交渉を持ちかける義務」というところまでは踏み込んでおらず、下請け側が声を上げないと動かないしくみです。中小零細の下請け事業者の “協議をもちかけることすらしない・できない”状況をどう思われますか。
〇もちろん、「親事業者にまで義務を課すのはやりすぎではないか」というご意見もわかります。自由競争、契約自由が経済の大原則ですし、交渉くらい自分で努力しろというのもわからなくはない。ただ、中小零細の下請け事業者にある、“声を上げたら仕事を失うかもしれない”という懸念を、やはり見過ごしてはならないと思います。
公正取引委員会が示した令和5年の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」でも、「発注者として採るべき行動/求められる行動」の中で、「受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の慣行に応じて1年に1回や半年に1回など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。」とされています。
もとより条文も、理由もなく協議しろと言っているのではなく、「給付に関する費用その他の事情が生じた場合において」としているのです。正当な理由があれば、指導や勧告を行わないという運用さえしっかりしていれば、社会的にインフレが生じている時など、親会社から協議をする責務を負わせてもよいのではないでしょうか。見解を伺います。
(まとめ)価格転嫁は一定程度進んできたとされますが、ここからは、転嫁の進まないところをどう進めるかが重要なのだと思います。価格転嫁を促す従来の取り組みも大事ですが、そうした中では、「自分からは言い出せない」という下請けをどうフォローするか、動かない親事業者をどう動かすか、さらに一歩踏み込んだ取り組みも考えていかないといけないのではないかと思います。そのことを指摘して、質問を終わります。
以上